空き家になる実家を相続したとき、まず最初に心配なのは相続税ではないでしょうか。
相続税は各種金融機関、税務署で、相続後10か月以内に支払わないといけません。
一昔前は、相続税と言えば資産家だけの話でした。
しかし2015年の法改正(「相続税基礎控除」の引き下げ)により、相続税を払わないといけない人が倍増しているそうです。
この記事では空き家を相続した場合、相続税がどれくらいになるのか、その仕組みと計算方法をざっくり書いています。
相続税は様々なケースに応じて、きめ細かくルールが枝分かれしています。
相続税の全体像を掴むのは至難の業ですが、この記事では「空き家相続」に特化していますので、比較的掴みやすいと思います。
また細部の話を伝えるために、全体の話をしなくてはならない事があります。
と感じる部分もあるかもですが、話を外枠から細部に切り込むためです。
「空き家の相続、全般」の話はこちらの記事にまとめてます。
【実家の空き家を相続したら】相続税の概要をおさえよう
空き家を相続したら、相続税を納めなくてはなりません。
相続税を納める人は相続した人、つまり「相続人」です。
相続税を考える前に、自分はどれくらいの割合の相続を受けるのか、を解らないといけません。
相続人は自分を含め、何人いるのか把握しておきましょう。
相続順位を知っておこう
相続人には順位があります。それを相続順位と言います。
例を挙げると、亡くなった人が「Aさん」だとして、「Aさん」には妻と長男、次男、長女がいたとします。
| Aさん(被相続人) | 妻 | ||||
| 長男 | 次男 | 長女 | |||
配偶者は順位に変動なく、常に相続人の権利があります。
そして、第一順位は子供たちです。
一般的に、相続順位は次のようになっています。
上の家族の例の場合・・
子供たち全員、もしくは誰か一人でも相続を受けた場合、第二順位と第三順位の人は相続人にはなりません。
第一順位の人が亡くなっている場合は、第二順位に移るんじゃなく、亡くなっている人の子供が第一順位になります。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
このように、本来相続人となるはずの人が亡くなっている時は、その子供(被相続人の孫)が、代わりに相続できます。
下の表では、「〇」が付いている人が、第一順位相続人となります。
被相続人の孫は、長男の「代襲相続人」となって、長男がもらえるはずの相続額と同額をもらえます。
| Aさん(被相続人) | 妻 〇 | ||||
| 長男(死亡) | 長男の嫁 × | 次男 〇 | 長女 〇 | ||
| 子供(Aさんの孫)〇 | |||||
この表であるように死亡した長男の嫁は、相続人となりません。
代襲相続は、「直系卑属(ちょっけいひぞく)」に継承されるからです。
直系卑属(ちょっけいひぞく)とは
■ 「直系」・・「先祖から子孫へ」血つながりの縦ライン
(養子縁組を交わした親子も「直系」です)
■ 「卑属」・・自分より下の世代 つまり子孫
「直系卑属」とは、自分より下の世代の「血つながりの人(血液的にも・法律的にも)」です。
嫁は血つながりでないので、直系卑属ではありません。
「第一順位の子供はいたけど、死亡している」という場合、代襲相続人に相続が移ることは解りました。
そのときの相続人は第二順位、「故人の親」へと移ります。
これも代襲相続で、生きていれば「故人の親の親」となるんですが、そんなケースはほぼありません。
そうなると第三順位、「故人の兄弟」が相続人となります。
第三順位にも、代襲相続人があり、故人から見て「甥や姪」が相続人になります。
| 故人 | ||
| 故人の兄(死亡) | 故人の兄嫁 × | 故人の弟 〇 |
| 兄の子(故人の甥) 〇 | ||
■ 相続人が亡くなっていた場合は代襲相続人が相続する
■ 順位の高い相続人が全員「相続放棄」すると、相続人は次の順位の相続人に移る
■ 順位の高い相続人がもともといない(独身や、子供を持っていない)場合、相続人は次の順位の相続人に移る
遺産相続の取り分割合い【法定相続分】を知っておこう
相続人が複数いる場合、故人との関係によって、割合いが法律で決まっています。
しかし、それは相続人同士で、もめたりトラブルになったとき、裁判などで示す基準として使われるためにあります。
なので、相続人同士で話し合い、みんなが「合意」すれば、法定相続分通りでなくても良いわけです。
これを「相続分割協議」と言い、通常は「相続分割協議書」を作ります。
法定相続分はどのようになっているか、参考にもなるので見てみましょう。
被相続人(故人)に、配偶者がいる場合の例です。
| 相続人 | 配偶者の貰う割合 | 配偶者以外の相続人が貰う割合 |
| 配偶者しかいない場合 | 財産の100% | |
| 配偶者と第一順位の人いる場合 | 財産の50% | 財産の50%を第一順位の人数で折半 |
| 配偶者と第二順位の人がいる場合 | 財産の2/3 | 財産の1/3を第二順位の人数で折半 |
| 配偶者と第三順位の人がいる場合 | 財産の3/4 | 財産の1/4を第三順位の人数で折半 |
配偶者がいない場合、の法定相続分はこうなります。
| 相続人 | 受け取る財産の割合 |
| 第一順位の人 | 配偶者がいないので100% |
| 第二順位の人 | 配偶者、第一順位がいないので100% |
| 第三順位の人 | 配偶者、第一順位、第二順位の人がいないので100% |
相続税の税率と控除を知っておこう
受け取る遺産額に応じて、支払う税率と控除額が決まっています。
| 受け取る遺産額
「正味の遺産額」 |
税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超え | 55% | 7,200万円 |
1人あたりの受け取り額に応じて、上の表のような税率と控除額とになります。
基礎控除額を知っておこう?
多くの空き家になる実家の場合、「小規模宅地等の特例」が使えません。
ただし相続税の場合は「基礎控除」というものがあります。
控除というのは「差し引く」という意味合いがあり、控除された金額分は「支払わなくて良い」という事になります。
基礎控除額は、下のように計算します。
例えば…
父親は5年前に亡くなっていて、今回実家で一人暮らしをしていた母親が亡くなったとします。
第一順位の子供たち3人が相続人だったら、下のように計算します。
3,000万+600万×3人=4,800万
相続人が相続する財産が、4,800万までなら相続税はかかりません
控除額4,800万を超えたら、超えた差額の金額に対して税金がかかります。
正味の遺産額はいくらか?
財産から借金などを差し引いて、手元に残る税金がかかる財産です。
▼▼▼▼▼
正味の遺産額=財産-借金-税金がかからないお金
では、それぞれの項目を簡単に解説します。
■預貯金
■現金
■株券
■お金に変えられる遺品
■不動産
■などなど…
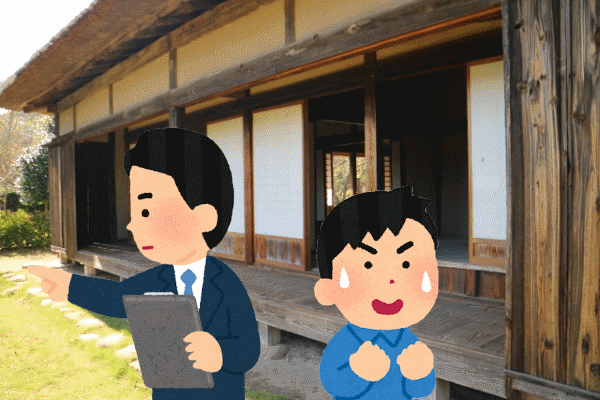
■ローンや借入金
■滞納家賃
■故人に届いた請求書の未払い分
■などなど…
■生命保険で降りた保険金のうちの
→500万×相続人の人数
(相続人が受け取った場合に非課税)
■死亡退職金のうちの
→500万×相続人の人数
(相続人が受け取った場合に非課税)
① 業務中の死亡の場合
死亡時の給与(各種手当含む)の3年分の金額が非課税
② 業務中以外で死亡の場合
死亡時の給与(各種手当含む)の半年分の金額が非課税
■などなど…
父親が亡くなり、子供3人が相続人だった場合
■ 財産
預貯金 1,000万
不動産 3,000万
■借金
借金 100万
■相続人に入った保険金と死亡退職金
生命保険金 8,000万
死亡退職金 2,000万
このケースでの「正味の遺産額」を出してみます。
1000万+3000万-100万+(8000万-500万×3)+(2000万-500万×3)
=1億900万
このケースの基本控除額は3000万+600万×3=4,800万です。
なので相続税がかかる金額は、
★課税対象額
10900万-4800万=6,100万
ではこれを遺産分割協議で、このように分けることになったとします。
■ 長男 不動産(3,000万円)と100万円
■ 次男 2,000万円
■ 三男 1,000万円
合計額 6,100万円
それぞれの相続税を見てます。
| 相続人 | 受け取り遺産額 | 税率 | 控除額 | 相続税 |
| 長男 | 3,100万円 | 20% | 200万円 | 3100×20%-200=420万円 |
| 次男 | 2,000万円 | 15% | 50万円 | 2000×15%-50=250万円 |
| 三男 | 1,000万円 | 10% | なし | 1000×10%=100万 |
ちなみに長男は不動産の3000万だけの受け取りにすれば、税率は15%になります。しかし控除額が50万に目減りするので、相続税は400万です。
あと、ここに出てくる不動産の価格は、実際に売買できる価格ではありません。
売れない、貸せない、の負動産だとしたら相続税でも足かせにもなり、今後の管理費や固定資産税でも、負担が続きます。
土地は現金のように価値を分けるのが難しく、とりあえず共有相続財産として複数人で持ち合うことも可能です。
しかし不動産の共有財産は、あとでトラブルの元となるケースが多いので、よく話し合いましょう。
相続時には実際の売買価格出なく、路線価で計算します。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
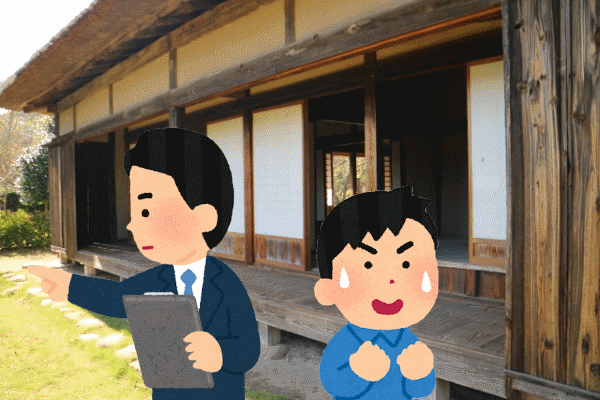
売りにくい不動産は、その手の物件に強い業者に相談すると良いです。
ここは一括査定を、無料で試せるサイトです。
まとめ
相続税は申告を間違えると余分に払ってしまったり、逆に過少申告になってしまったりと、大きなお金が動くのでミスなくやりたいところです。
今回の記事は、ざっくり税額の予想をつける意味で参考にして、正確なところは税理士さんにお願いするのがベストです。
税理士費用は、およそ相続額の1%が相場と言われています。
そこで最後に、税理士費用を少しでも安く抑えるための、お薦めサービスを2つ紹介します。
一つは、何度でも税理士さんに相談できる環境で、「自分で相続税申告書」を作成できるサイトです。
料金は69,000円ですが、税理士報酬に比べると桁違いに安いです。
▶▶▶ 自分で簡単に相続税申告書を作成。申告の難易度をまずはWEB診断。【better相続】
![]()
そしてもう一つ、「税理士さんにお願いしたい!」という人は、税理士選びに失敗しないよう、下のサイトがお薦めです。
P.S.
記事の本質が「空き家になった不動産の相続」というものでしたが、記事を書いているうちに、ざっくりと全体像を書かないと難しいと気づきました。
本来の「空き家相続」のケースでは、あまり起こらないケースまで書いてしまいました。
ざっくりとでも相続税のこと、伝わりましたでしょうか。
「空き家相続とは関係ない」ついでにもう1つ。
配偶者の相続税控除額は「配偶者控除」といって、手厚くなっています。
➀配偶者の法定相続分
➁1億6,000万円
➀と➁のどちらか多い方が、配偶者が控除を受けられます。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
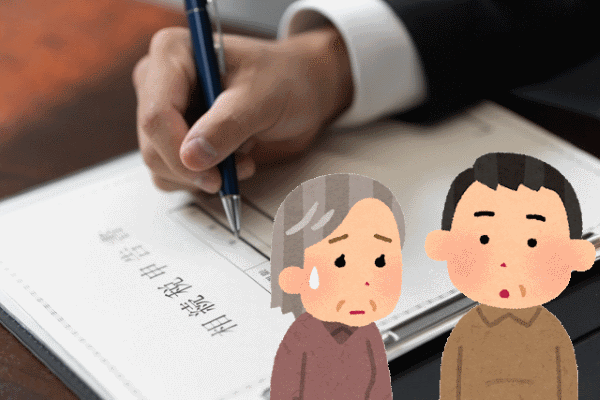
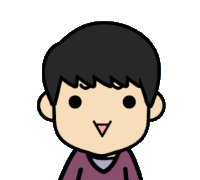
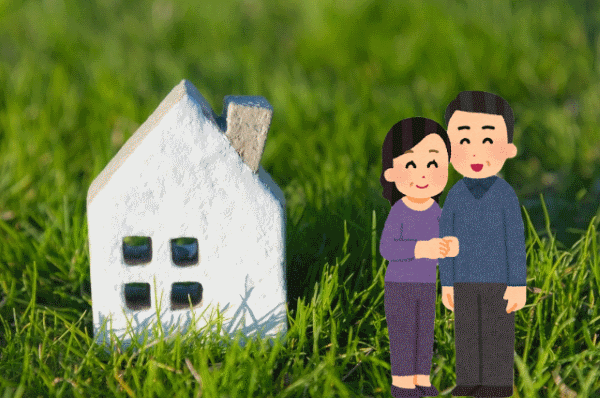
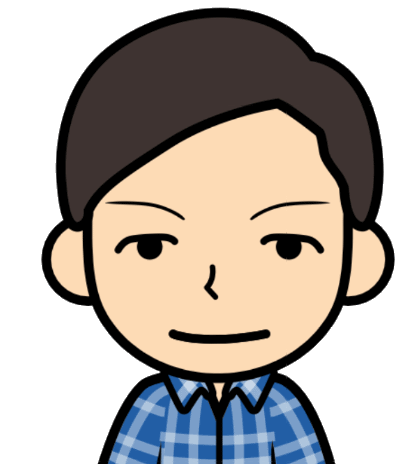
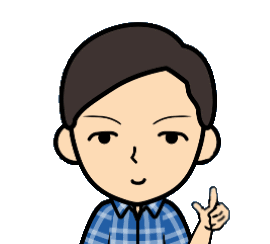
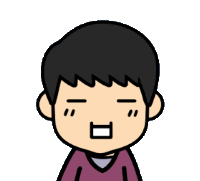
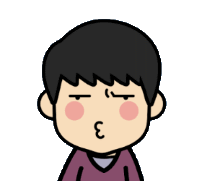
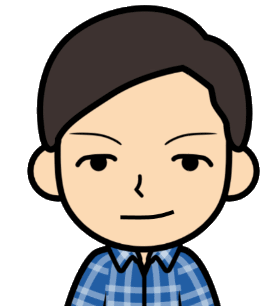
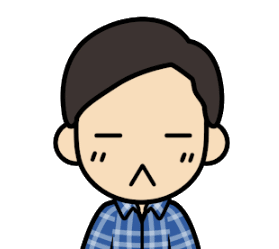
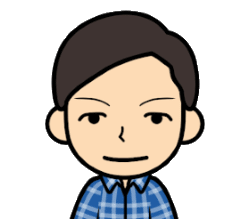
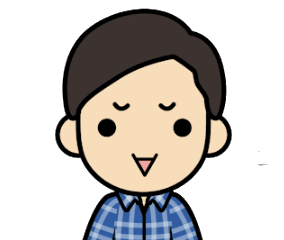
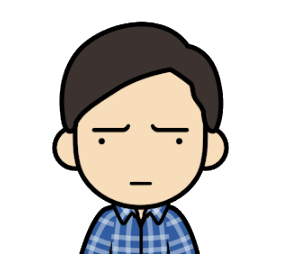
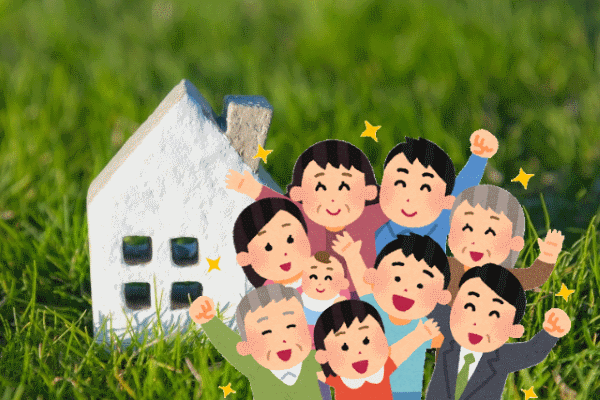
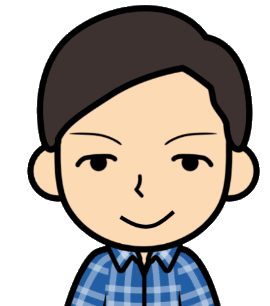
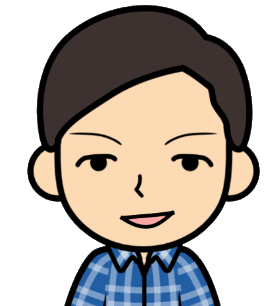
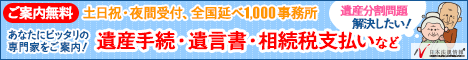

コメント